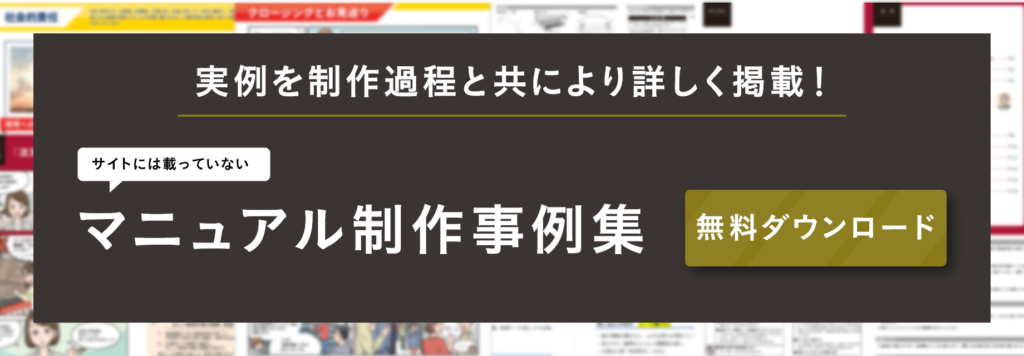退職や異動の際に欠かせないのが「引き継ぎマニュアル」です。しかし、多くの企業では「作ったはいいけれど後任者が読まない」「情報がうまく伝わらない」といった問題が発生しています。
そこで本記事では、わかりやすく実用的な引き継ぎマニュアルを作成する方法や、後任者がしっかり活用できる工夫について解説します。
目次
引き継ぎマニュアルの重要性
なぜ引き継ぎマニュアルが必要なのか?
引き継ぎマニュアルは、業務のスムーズな移行を支える重要なツールです。退職や異動によって業務の担当者が変わる際、マニュアルがあることで後任者が業務を正しく理解し、迅速に対応できるようになります。
特に、属人的な業務が多い場合、口頭での引き継ぎだけでは十分な情報共有ができないため、文書化が不可欠です。
読まれない引き継ぎマニュアルが引き起こすリスク
引き継ぎマニュアルが読まれないと、業務の停滞やミスが発生しやすくなります。特に、細かい手順や注意点が共有されないと、クライアント対応のミスや法令違反のリスクも高まります。
また、後任者がマニュアルを読まずに試行錯誤を繰り返すことで、業務効率が低下し、余計なコストがかかる可能性があります。
わかりやすい引き継ぎマニュアルの作り方【基本編】
基本構成と記載すべき項目
引き継ぎマニュアルを作成する際は、一般的な業務マニュアルと同様に、まずは記載範囲を決めていく必要があります。
具体的には、以下の項目を整理して記載すると良いでしょう。
- 業務の概要:業務の目的や全体像
- 業務フロー:具体的な手順を時系列で整理
- 使用ツール・システム:必要なソフトウェアやログイン情報
- トラブルシューティング:よくある問題とその対処法
- 担当者情報:問い合わせ先や関連部署
▼業務マニュアルの作成手順については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
後任が理解しやすい文章の書き方
また、後任者が迷わず業務を遂行できるマニュアルを作成するうえでは、以下のポイントを意識しましょう。
- 簡潔で明確な表現を使う:専門用語はできるだけ避け、簡単な言葉で説明する。
- 箇条書きを活用する:情報を整理し、視認性を向上させる。
- 具体例を示す:実際の業務フローを示すことで理解を深める。
- 図や表を挿入する:文章だけでなく、視覚的に伝える工夫をする。
▼使いやすいマニュアルのポイントについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。
後任者がマニュアルを読まない理由と解決策

なぜ後任者は引き継ぎマニュアルを読まないのか?
引き継ぎマニュアルは、後任者がスムーズに業務を引き継ぐために作成されるものです。しかし、せっかく作ったマニュアルが読まれずに、無駄になってしまうケースも少なくありません。
読まれない理由はさまざまですが、具体的には以下のようなものがあります。
- 情報量が多すぎる:文章が長すぎて読む気が失せる。
- 業務の流れと合わない:実際の業務とマニュアルの順序が異なる。
- 視覚的な要素が不足:文字ばかりで内容を把握しにくい。
- 更新されていない:古い情報のままで、参考にならない。
読まれる引き継ぎマニュアルにするための工夫
マニュアルを作成するには、多くの手間と労力がかかりますが、せっかく作成するなら活用されるマニュアルにしたいものです。以下のような工夫をすることで、読みやすく実用的なマニュアルになり、引き継ぎを円滑に進められるようになります。
- 動画マニュアルの活用:操作方法などは動画で説明する。
- フローチャートの導入:業務の流れを図で示す。
- 簡潔な文章でポイントを押さえる:重要な情報のみを抜粋し、詳細は別資料にまとめる。
- 定期的な更新を実施:情報を常に最新の状態に保つ。
▼フローチャートについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。
引き継ぎマニュアルの作成手順【実践編】
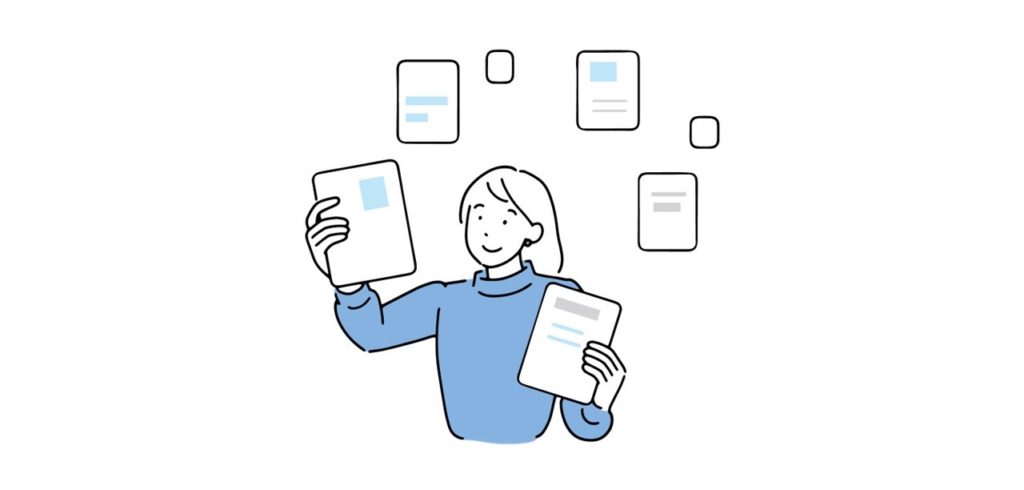
作成前に準備すべき情報
引き継ぎマニュアルを作成する前に、まず必要な情報を整理することが大切です。業務の全体像を把握し、何をどの順番で伝えるべきかを明確にしましょう。
例えば、営業職の場合、顧客リストや商談履歴、成約時のポイントなどを整理しておくと、後任者はスムーズに業務を引き継ぐことができます。また、業務で使用するツールやシステムの操作方法を記載し、実際の画面キャプチャを用いることで、よりわかりやすいマニュアルになります。
▼営業マニュアルの作成手順については、以下の記事で詳しく解説しています。
作成手順
ステップ1 業務フローの整理
業務の流れを時系列で整理し、どの順番で作業を進めるかを明確にします。
例えば、経理業務なら「請求書の受領→支払い処理→月次決算」といった流れを図解で示すと、後任者が直感的に理解しやすくなります。また、業務ごとに優先度や頻度を記載しておくことで、どこから取り組むべきかもわかりやすくなるでしょう。
ステップ2 マニュアルのフォーマット選定
マニュアルは文章だけでなく、図や表、動画などを組み合わせて作成することで理解が深まります。例えば、システムの操作手順を伝える場合、動画で実際の操作を見せたり、画面キャプチャ付きの手順書を作成するなど、視覚的に伝える工夫が有効です。また、紙のマニュアルだけでなく、デジタルフォーマット(PDFやクラウド上のドキュメント)を併用すると、後任者が必要なときにすぐにアクセスできるようになります。
ステップ3 具体的な記述ルールを決める
統一されたフォーマットでマニュアルを作成することで、読者は内容を理解しやすくなります。例えば、業務ごとの手順を箇条書きにするのかフローチャートにするのかを決め、表現のブレをなくしましょう。また、専門用語が多すぎると後任者の理解を妨げるため、できるだけ平易な言葉で記述すると良いでしょう。「誰が」「何を」「どのように」行うのかを明確にすることも重要です。
ステップ4 後任者・責任者に確認&改善
マニュアルを作成したら、後任者や責任者に実際に読んでもらい、わかりにくい点がないかを確認してもらいましょう。例えば、「この部分の説明が不足している」「手順が多すぎて混乱する」などのフィードバックがあれば、それを反映して改善します。また、試験的にマニュアルを使って業務を進めてもらい、問題がないかチェックするのも効果的です。
引き継ぎマニュアル運用のポイント

マニュアルを定期的に更新する
引き継ぎマニュアルは一度作成したら終わりではなく、業務の変化に応じて更新することが重要です。例えば、新しいツールの導入や業務フローの変更があった際に、古い情報のまま放置されると、後任者が誤った手順で作業を進めてしまうリスクが考えられます。定期的に内容を見直し、必要に応じて修正を加えることで、常に最新の情報を維持し、実用性を高めることができるでしょう。
また、更新担当者を決め、責任を明確にすることも重要です。チームリーダーが年に一度マニュアルの見直しを行い、最新情報を反映するなどの対策をとることで、情報の鮮度を保つことができます。
さらに、従業員からのフィードバックを定期的に収集し、実際の使用感や改善点を反映することで、より実用的なマニュアルへと進化させることができます。
後任者へのフォローアップ
マニュアルを活用してもらうためには、作成後のフォローアップも欠かせません。後任者へのマニュアルの使い方を説明する時間を設けることも重要です。
また、業務の進行に応じた定期的なミーティングを実施し、わからない点を確認しながら実践的に学べる環境を整えると良いでしょう。
さらに、マニュアルの内容をデジタル化し、検索しやすい形でクラウド上に保存することで、後任者が必要な情報にすぐアクセスできるようにする工夫も有効です。例えば、「経理業務の処理方法」などのキーワードで簡単に検索できるようにすると、実際の業務の中でスムーズに活用できるようになります。
まとめ
引き継ぎマニュアルは、後任者がスムーズに業務を引き継ぐための重要なツールです。読みやすさやわかりやすさを意識して作成し、実際に活用されるような工夫を施すことで、業務の円滑な移行を実現できます。
ぜひ、本記事を参考に、実用的な引き継ぎマニュアルを作成してみてください。