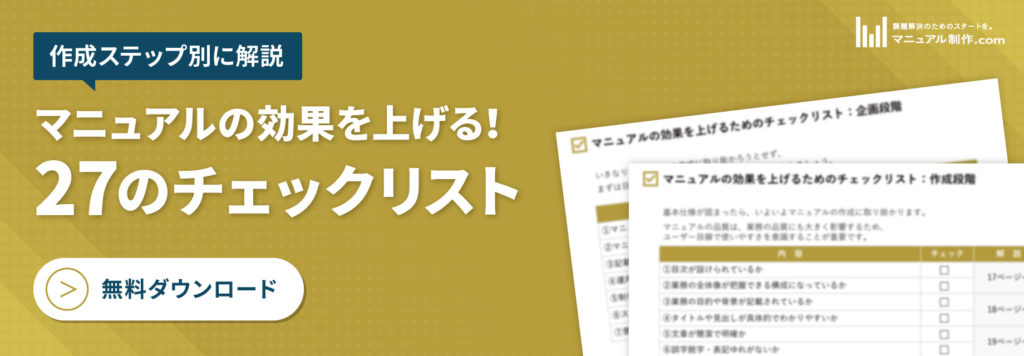業務の流れを分かりやすく共有したいのに、文章だけではうまく伝わらない――そんなときに役立つのが「フローチャート」です。読み手の目線に合わせて手順を可視化することで、理解のばらつきが減り、情報共有や教育、業務改善をスムーズに進めることができます。
とはいえ、いざフローチャートを作ろうと思っても「何から手をつけていいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、初めての方でも迷わないフローチャートの作り方・書き方を、5つのステップで簡単に解説します。
目次
フローチャートとは?用途とメリット
まずは、フローチャートの意味や活用シーン、導入によって得られる効果を、初めての方にも分かりやすく整理していきましょう。
定義と基本の考え方
フローチャートとは、業務の手順や判断を「記号」と「矢印」で表現し、誰が見ても同じ順序でたどれるようにするための図解です。
基本的には「開始/終了」「処理」「判断」「矢印」という最小限の要素だけでも十分に機能します。目的は“見た目のきれいな図”を作ることではなく、“誤解のない共通理解”を素早く得ることです。
図にするメリット
文章だけでは、読み手の知識や解釈によって受け取り方に差が生じやすいですが、フローチャートでは、流れ・分岐・例外を視覚的に示せるため、解釈のブレを抑えられます。結果として、レビューが進みやすくなり、教育や引き継ぎの場面でも同じ手順を再現しやすくなります。
具体的には、次のような効果が期待できます。
- 認識合わせの迅速化
用語の曖昧さや思い込みを低減し、共通理解を得やすくなる。
- 抜け漏れ・ムダの発見
ボトルネックや手戻り箇所が見える化され、改善のヒントが見つかる。
- 教育・引き継ぎの負担軽減
手順や判断基準を短時間で共有できる。
- 品質・コンプライアンスの担保
チェックポイントや承認ステップを確実に管理できる。
- 運用の柔軟性
紙・Excel・PowerPointなど、環境に合わせて作成・更新・共有ができる。
フローチャートでよく使われる記号・図形とその意味
ここでは、フローチャートでよく使われる記号や図形の役割・意味・使い方をご紹介します。
形(名称) | 例 | 使い方・ポイント |
端子(開始/終了) | 「開始」「終了」 | 原則、図内には1つの「開始」と1つの「終了」を置く |
処理(プロセス) | 「在庫を確認する」 「見積を送る」 | 動詞で具体的に記述する(名詞止めにしない) |
判断(条件分岐) | 「在庫は足りているか?」 | 分岐はYes/Noなどで統一し、行き止まりを作らない |
線・矢印 | 「処理 → 判断」 | ・向きは上→下(または左→右)に統一し、線の交差は避ける ・すべての矢印は次の記号または終了に接続する |
データベース(システム) | 「在庫DBを更新する」 | “どのデータをどうするか”を動詞で明確に表す |
接続(ページ外結合子) | 「→ p.2-A」 | フローチャートが複数ページにまたがる際に使用し、記号内にはページ番号などを記載する |
ループ | 「在庫がなくなれば終了する」 | 繰り返し行う作業や処理を表す |
定義済み処理 | 「返品処理(別チャート)」 | 特定の作業や処理を別フローとして分けて記載する場合に使用する |
保存・保管 | 「第二倉庫」 | 文書や帳票など、保存・保管が必要な作業を表し、記号内には保管場所を記載する |
手動入力 | 「顧客情報を入力する」 | システムへの手入力が必要な作業を表す |
複雑な記号を増やしすぎると、かえって読み手は迷ってしまいます。迷ったときは「開始/終了」「処理」「判断」「矢印」の4つだけで構成してみましょう。多くの実務フローはこれらの記号だけで十分に表現できます。
▼フローチャートの記号や種類について、詳しくは以下のページでご紹介しています。
作る前に決めておきたいこと
よいフローチャートは、作り始める前の準備でほとんどが決まります。ここでは「誰のために/何のために/どこまで描くか」を明確にし、「情報の粒度」と「命名のルール」を整理しておくことで、短時間でも分かりやすく仕上げるための土台を整えます。この準備をしておくと、後の作成ステップやツール操作がスムーズになり、手戻りも減らせるでしょう。
目的・対象読者・範囲を決める
まずはじめに、「目的」「対象読者」「範囲(始点/終点)」を1枚のメモにまとめておきましょう。目的が曖昧なまま描き始めると、記号や線ばかり増えて、結局何を伝えたいのか分からない図になってしまいがちです。
目的
“何を達成したいのか”を一文で定義します。
【例】新人が問い合わせの一次対応を自走できるようにする。
対象読者
誰が読むのか、どの程度の知識を持っているのかを想定します。
【例】配属1か月以内の新人。
範囲
始点/終点を明確にし、含めない領域も定義します。
【例】始点=問い合わせメール受信、終点=顧客へ解決報告。
メモを作成する際には、
・目的が“動詞”で書かれているか(例:〜できるようにする)
・読者の前提と用語レベルが定義されているか
・始点と終点が一目で分かるか
を意識しましょう。
情報の粒度と命名のルール
「粒度」とは、どの程度の細かさで分けるかという基準です。最初は「1記号=1処理」に統一し、同じレベルで並べましょう。
処理名は、動詞で簡潔に表記し、判断記号は条件文で書いてYes/Noを明示します。これだけでぐっと分かりやすいフローチャートになります。
命名のルール基本
【書き方の例】
処理:「在庫を確認する」「見積を送る」「注文をキャンセルする」
判断:「在庫は足りているか?」「与信は承認済みか?」
【NG例】
・「在庫確認」(名詞のみ)
・「すぐに丁寧に確認する」(副詞が多く曖昧)
【名詞→動詞への書き換え例】
✕ メール送信 → 〇 メールを送る
✕ 不備対応 → 〇 不備を修正する
✕ 承認依頼 → 〇 承認を依頼する
簡単5ステップ! フローチャートの作り方
ここからは、初めてでも迷わず仕上げられるように、最小限の記号で進めるフローチャート作成の5ステップをご紹介します。「文章の整理 → 図形への置き換え → 体裁を整える → 見直す」という流れで進めると、短時間で伝わるフローチャートを作成できます。
① 手順を洗い出す(文章でOK)
最初は図にせず、担当者からヒアリングした内容を、一文一行・動詞で書き出して並べます。
【例】
・問い合わせメールを受信する
・FAQを検索する
・回答テンプレートを作成する
・解決しなければ二次対応にエスカレーションする
この段階では、すべての例外を洗い出す必要はありません。まずはよく起きる流れだけを書き出すのがポイントです。
② 時系列に並べ、分岐候補に印をつける
書き出した内容を時系列に並べ替えましょう。判断が必要な箇所には★などの印をつけ、「何を基準に分かれるのか」を一言添えておきます。
印が3つ以上連続する場合は、あとで別チャートに分ける前提で、無理に詰め込まないのが安全です。
③ 文を記号に置き換える
ここで初めて図形にします。
- 行為→「処理」
【例】在庫を確認する
- 条件→「判断」
【例】在庫は足りているか?
- 開始/終了→「端子」
- 矢印は上→下(または左→右)に統一
④ 配置・配線を整える
矢印の流れは一方向に統一し、判断から出る線は「右=Yes」「下=No」など、ルールを固定しましょう。線が交差する場合は、記号の位置を入れ替えて調整します。
最終的に、行き止まりの矢印がないこと、開始と終了が一つずつあることを確認してください。
⑤簡素化とレビュー
最後に、表現の統一と粒度の調整を行います。
【例】
・名詞止めを動詞に直す(×在庫確認 → 〇在庫を確認する)
・判断は質問文にし、Yes/Noラベルを明示する
・1つの長方形に2つ以上の動作が入っていないかを確認する
可能であれば、前提知識のない第三者に確認してもらい、客観的な目線からレビューをもらうのが良いでしょう。
まとめ
フローチャートは、業務の流れや判断基準を分かりやすく共有するために非常に有効なツールです。
ポイントは、描き始める前に「目的」「対象読者」「範囲」を決め、「情報の粒度」と「命名のルール」をそろえること。あとは今回ご紹介した5つのステップに沿って組み立てれば、短時間でも“伝わる1枚”が作成できます。
この記事を参考に、ぜひフローチャート作成に取り組んでみてください。