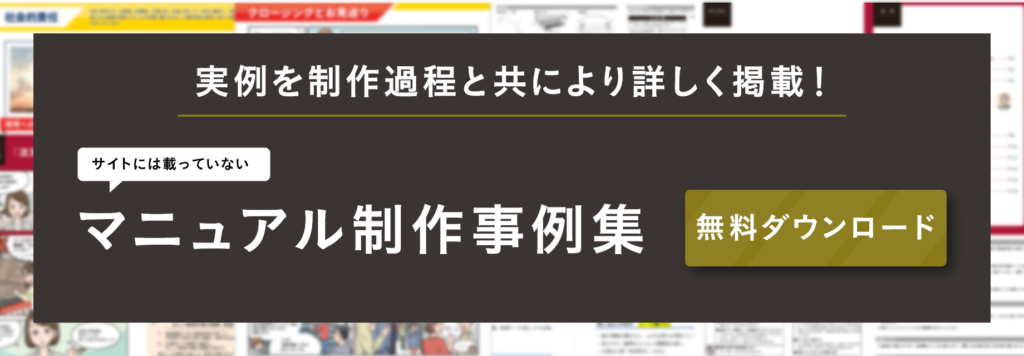業務の流れやルールを包括的にまとめたマニュアルは、人材育成や業務効率化に必要不可欠です。しかし、よく似たツールである手順書との違いはご存知ですか?
どちらも業務上必要な情報がまとめられていますが、実はそれぞれ目的や役割、内容が異なっています。
この記事では、マニュアルと手順書の違いを「作成の目的」「用途・役割」「内容・要素」という3つの観点から解説し、手順書作成における4つの重要なポイントと具体的な作成方法についてご紹介していきます。
目次
マニュアルとは
マニュアルとは、従業員が業務全体を理解できるよう、業務の概要や手順、ルール、ノウハウなどを網羅的にまとめたものです。用途にあわせて「業務マニュアル」「営業マニュアル」「教育マニュアル」など、さまざまな種類に分類されます。
マニュアルを作成することで、従業員の業務理解が深まるとともに、業務基準が明確化され、人材育成や業務の品質向上に役立ちます。
手順書とは
手順書とは、特定の作業や操作に関する具体的な工程や手順を細かくまとめたものです。手順書に従うことで、誰でも同じ品質で作業を遂行できるように設計されています。
手順書がない場合、作業者ごとに異なる方法で進められ、品質のばらつきやミスの原因となることがありますが、手順書を作成することで、業務手順が統一され、品質の安定化に役立ちます。
マニュアルと手順書の違い
作成の目的
マニュアルは、業務全体への理解を深め、従業員が業務全体を俯瞰しながら目標達成や課題解決を目指すことを目的としています。
一方で、手順書は、業務内の特定の作業に焦点を当て、その手順を詳細に記載することで、作業を安定的に行い、品質のばらつきを防ぐことを目的としています。
用途・役割
マニュアルには大きく分けて二つの役割があります。
一つ目は、ノウハウの共有と保存です。マニュアルを作成することによって、個々の従業員が持つ知識やスキルを組織全体で共有することができます。
二つ目は、業務の標準化です。業務全体の流れやルールを明確化することで、従業員に業務への俯瞰的な理解を促すことができます。
それに対して、手順書の役割は、業務遂行における具体的な手順や基準を明示し、従業員が迷わず作業できるようサポートすることであると言えます。
内容・要素
マニュアルと手順書はそれぞれの目的や役割が異なるため、記載する内容や情報量、範囲も異なります。
マニュアルは業務全体の概要や背景、ルール、ノウハウなど、広範囲な情報を網羅的に記載します。作業手順もその一部として含まれますが、あくまで業務全体の理解を補完するものです。
一方で、手順書は特定の作業に特化しており、フローや品質基準、注意点などが詳細に記載されています。マニュアルに比べると情報の範囲は限定的ですが、その分具体的で実践的な内容が記載されています。
マニュアルと手順書を比較すると、マニュアルのほうが情報量が多く、幅広い情報をカバーしていると言えるでしょう。
手順書の作成方法
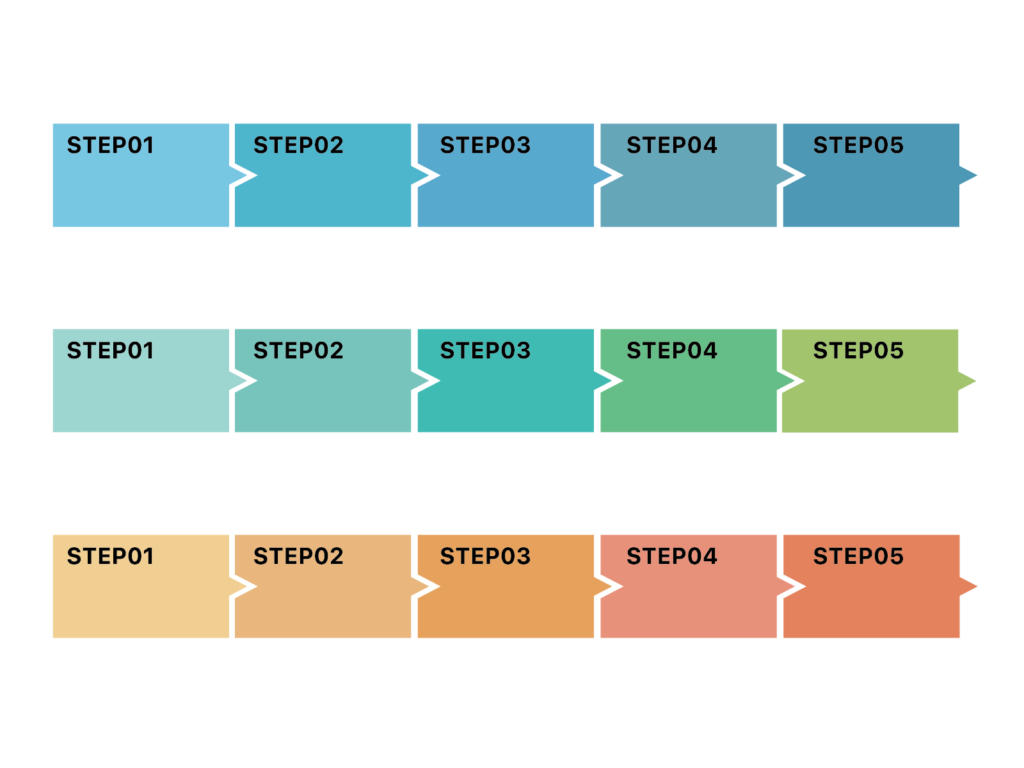
①業務の棚卸しと情報の整理
手順書を作成する際は、業務を棚卸しして、実際の業務に基づいて情報を整理することが重要です。
まずはどの作業に対して手順書を作成するのかを明確にし、作業者が理解しやすいよう、具体的な情報を整理します。現場の状況やニーズを把握し、作業を細分化して詳細に記述することを意識しましょう。
手順書に記載すべき情報は、主に以下のとおりです。
・作業の名称
・作業の目的
・作業の手順
・準備内容
・作業の具体的な内容
・判断基準
・注意点
②構成の検討
実際に手順書を作成する前に構成を考えることで、内容の見落としやばらつきを防ぎ、一貫性のある手順書を作成することができます。棚卸しした業務を整理し、時系列に沿って手順をリストアップすると、業務のアウトラインが捉えやすいでしょう。
この段階で、非効率な手順や作業があれば見直し、改善することも重要です。シンプルかつわかりやすい構成を目指しましょう。
③原稿の作成
ここまでに整理した情報と検討した構成をもとに、手順書の原稿を作成していきます。原稿作成にあたっては、以下の点を意識して進めましょう。
端的にまとめる
冗長にならないよう、必要な要点だけをできるだけ短い文章で記載しましょう。重要な情報を具体的かつ簡潔に伝えることが大切です。
見出しや箇条書きの活用
見出しや箇条書きを使うことで、視覚的にも情報が整理され、読み手にとって理解しやすい手順書になります。
図やイラストの準備
作業手順をわかりやすく伝えるために、原稿作成と並行して、図や写真、イラストなど視覚的に情報を補足する素材も準備しましょう。
ヒアリングの実施
実際に業務を行う担当者にヒアリングを行い、実務に即した情報やポイントを盛り込みます。これによって、実用性の高い内容になります。
▼ヒアリングの進め方やポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。
④フィードバックと修正
手順書の原稿がある程度完成したら、実際に従業員に仮運用してもらい、わかりにくい箇所や実情との乖離がないかを確認しましょう。修正点などのフィードバックがあればその都度対応し、必要な改善を加えていきます。
仮運用をすることで、作成段階では気づけなかったミスを発見できるケースも多いです。一度で完璧な手順書を作ろうとするのではなく、仮運用を繰り返しながら、段階的に改善を重ねることで、より使いやすい手順書になります。
⑤定期的な更新
手順書は完成後も定期的な見直しが必要です。作業内容の変更や新しい手法が導入された際には、手順書を随時更新し、常に最新の情報が反映されているようにしましょう。
手順書作成のポイント
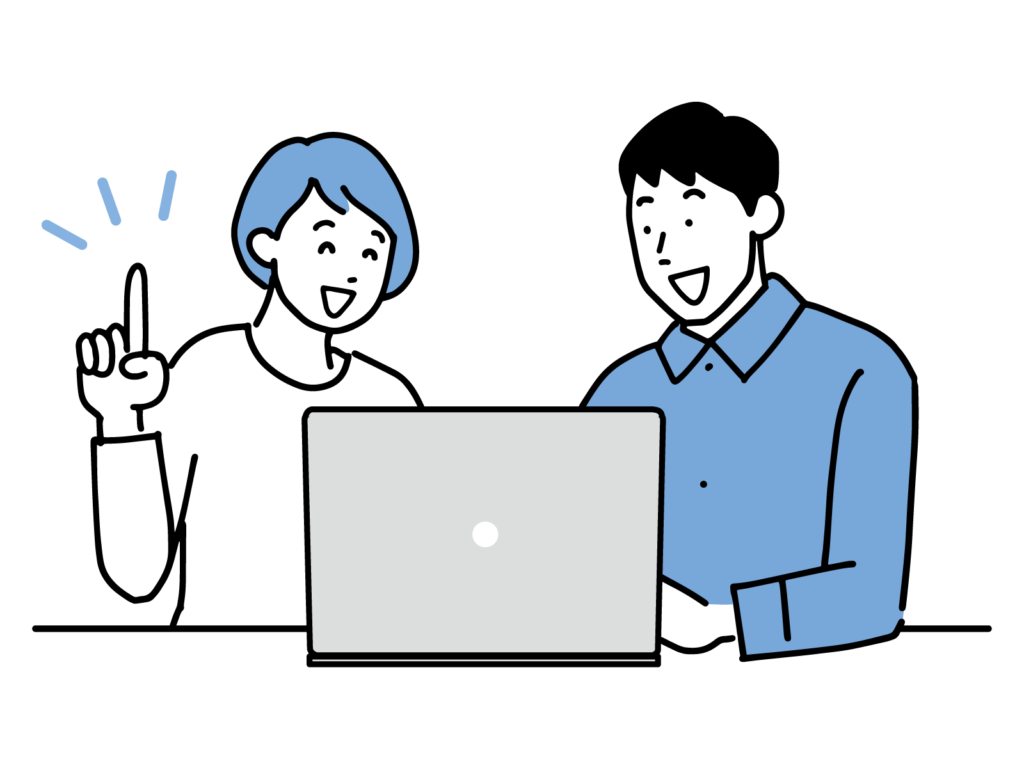
①作業内容を具体的に記載する
手順書では、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識した文章を心がけましょう。例えば、「在庫が減ったら補充する」という曖昧な表現ではなく、「在庫が50個を下回ったら、青い棚から10個補充する」といった数値や見た目などの具体的な基準を示しましょう。また、正しい作業と誤った作業それぞれの結果を記載することで、従業員が作業の成否を判断しやすくなります。
②情報を詰め込みすぎない
手順書において具体性は大切ですが、あまりにも多くの情報を詰め込みすぎてしまうと、本当に伝えるべき要点が埋もれてしまうことがあります。手順書には、業務手順に直接関連する内容のみを端的にまとめましょう。背景や詳細なプロセスの記載が必要な場合は、マニュアルと併用してバランスを取るのも一つの方法です。
③誰でも理解できるように書く
手順書の主な読み手は、新入社員や異動してきたばかりの社員です。そのため、業務に不慣れな人でも理解できるよう、専門用語や略称の使用を避けるなど、わかりやすい表現を意識しましょう。
また、手順を文章だけで説明すると理解しづらい場合もあるため、視覚的に業務を整理することも重要です。例えば、実際の作業風景の写真や操作画面のスクリーンショット、作業フローの図などを文章とあわせて記載することで、読み手が作業内容をよりイメージしやすくなります。
④デザインにこだわりすぎない
わかりやすく情報を伝えるためには、フォントやレイアウトなどのデザインも重要ですが、過度にこだわりすぎると、伝えたい情報がデザインの影に隠れてしまい、本来の目的が見失われることがあります。
読み手にとって最も大切なのは、必要な情報を迅速かつ正確に得られることです。デザインはあくまで補助的な要素として扱い、必要な情報が効率的に伝わることを最優先に考えましょう。
まとめ
今回は、マニュアルと手順書の違いと、手順書の作成方法、作成時のポイントについて解説しました。
これらのポイントを押さえることで、無駄のないシンプルでわかりやすい手順書を作成でき、業務の効率化や品質の均一化といったさまざまなメリットを享受することができます。ぜひこの記事を参考に、より効果的な手順書を作成して業務に活用してください。