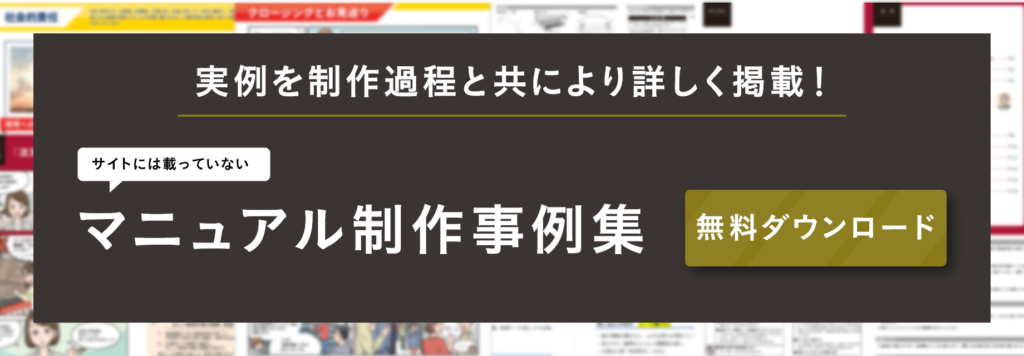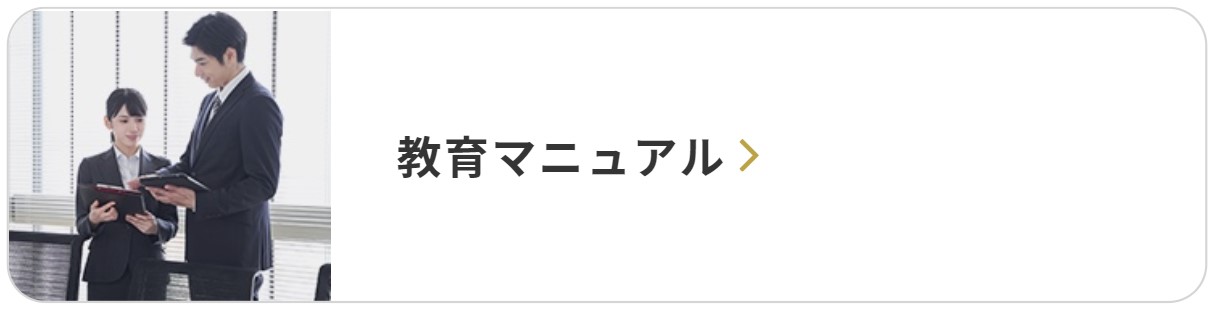新人教育マニュアルを作成するメリット
業務内容が定着しやすくなる
マニュアルを整備することで、業務の流れや全体像が明確になります。口頭説明やOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)では理解が難しい複雑な作業や工程も、マニュアルを活用することで視覚的に把握しやすくなり、新人でも業務内容をスムーズに理解できるようになります。
さらに、口頭説明やOJTでは、メモを取りきれなかったり、聞き逃してしまうこともありますが、マニュアルがあれば、曖昧な部分や忘れてしまった部分を後からいつでも確認することが可能です。これにより、業務内容が定着しやすくなります。
教育の効率化
口頭説明やOJTの場合、教える人によって内容が異なったり、教育内容に漏れが生じる場合がありますが、マニュアルを導入することで、指導内容が統一され、教育の質を一定に保つことが可能になります。教育担当者の教え方やノウハウに依存せず、効率よく教育を進めることができます。
また、教育担当者はマニュアルをもとに教育を進められるため、一からすべてを説明する手間が省け、教育にかかる負担の軽減にもつながります。
業務品質の標準化
統一された教育内容が正しく定着することで、新人が判断に迷ったり、自己流で作業を進めることが減り、業務品質のばらつきが軽減されます。
「マニュアルを見ればわかる」という環境を作ることで、新人であっても安定的に業務を遂行することができるでしょう。
新人が業務をしっかりと身につけることで、早期に即戦力として活躍することも期待できます。
新人教育マニュアルに必要な5つの項目
ビジネスマナー
どの職種であっても、最低限のビジネスマナーは必要不可欠です。特に社会人経験が少ない新人にとっては、業務の基礎となる重要な部分と言えます。
マニュアルに記載する具体的なビジネスマナーの例としては、以下が挙げられます。
・挨拶
・コミュニケーションの取り方
・身だしなみや服装
・言葉遣い
・名刺交換の方法
・電話応対
・メールの基本
すでに社会人経験がある人にとっては基本的な内容であっても、新人にとっては初めて学ぶことも多いでしょう。また、会社独自のマナーがある場合は、それも含めて丁寧に解説することが重要です。
企業理念や方針
会社が大切にしている価値観や目指すビジョンは、マニュアルに記載しておきたい重要な項目です。
これらは業務そのものには直接関係しない場合もありますが、会社の一員として理解しておくべき内容です。また、業務を進めるうえで、行動の指針にもなります。
社内ルール
新人が最初に知っておきたいのが、会社独自のルールです。これらの情報はインターネットで調べることができないため、業務を円滑に進めるためにマニュアルにまとめておくことが求められます。
具体的な例としては、以下が挙げられます。
・出退勤に関するルール
・経費精算や各種手続き
・備品の管理方法
・福利厚生
・評価制度
社内ツールの使用方法
勤怠管理システムやチャットツール、Web会議システムなど、社内で共通して使用するツールがある場合は、それらの基本的な使い方をマニュアルにまとめましょう。操作画面のキャプチャがあると、さらにわかりやすいマニュアルになります。
加えて、ファイルの保存場所や命名ルールなどが決まっている場合は、それらもあわせて記載することで、混乱を防ぐことができます。
業務の全体像と内容
新人が担当する業務の全体像をまとめます。
新人教育マニュアルにおいては、担当業務の社内での位置づけや他部署との関係性など、業務の全体像をつかめるようにすることが重要です。これによって、担当業務の目的や役割がより深く理解できるようになり、業務を円滑に進めることができます。組織図を活用するのもよいでしょう。
ただし、業務フローや詳細な作業内容をすべて新人教育マニュアルに記載すると、情報量が多くなりすぎるおそれがあります。マニュアルが膨大になると、その分必要な情報を見つけにくくなったり、煩雑になりやすいため、詳細な業務内容は別の業務マニュアルとして分けて作成し、必要に応じて参照できる形にするのも一つの方法です。
▼業務マニュアルの作成方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
新人教育マニュアルの作成方法
1.目標を設定する
新人教育マニュアルを作成する際は、まず新人に期待する成果や到達してほしいレベルなどのゴールを明確にします。初めに目標を定めることで、マニュアルに盛り込むべき範囲や必要な情報も整理しやすくなります。
また、冊子形式で配布するのか、データで共有するのかといった運用方法もあらかじめ決めておきましょう。
2.項目ごとに記載内容を整理する
新人教育マニュアルに必要な「ビジネスマナー」「企業理念」「社内ルール」「社内ツールの使い方」「業務の全体像」といった主要な項目ごとに、記載する内容を洗い出し、全体の構成を固めます。
例えば、ビジネスマナーの項目では、服装や髪型の規定、言葉遣い、電話やメールのマナーなど、マニュアルに記載すべき情報をリストアップし、それぞれの詳細を整理します。
3.原稿を作成する
必要な情報を整理し構成が固まったら、具体的な原稿の作成に進みます。
原稿作成時には、以下のポイントを意識しましょう。
誰が読んでも理解できる内容にする
新人教育マニュアルは、誰が読んでも理解できることが重要です。専門用語や社内独自の用語も、新入社員には馴染みがない場合が多いため、できるだけ使用を避け、他の言葉に言い換えるようにしましょう。専門用語を使用する場合は、注釈や解説を入れるとよいです。
また、曖昧な表現や誤解を招く表現はミスの原因にもなるため、簡潔でわかりやすい文章を心がけましょう。
業務の全体像が把握できるようにする
先述のとおり、新人教育マニュアルにおいては、業務全体の流れがわかる構成にすることが重要です。
業務内容を説明する際にも、詳細な情報まですべて網羅しようとするよりも、「なぜこの業務を行うのか」「前後の業務とどのように関係しているのか」といった一連の流れや前後関係がわかるような構成にすることを優先しましょう。
視覚的な要素を活用する
図やイラスト、写真などの視覚的な情報を取り入れることで、文字だけでは伝わりにくい内容も理解しやすくなります。また、文字だけのマニュアルに比べて、新人の心理的ハードルも下がります。複雑な業務は、動画を活用するのもおすすめです。
さらに、重要な箇所は太字にしたり、色付けすると、スムーズに情報を得られるようになります。
判断基準を明確にする
業務フローや作業内容を記載する際は、「どうなれば完了なのか」「どのような状態が異常なのか」など、判断基準を明記しましょう。
例えば、「この画面が表示されたら処理完了」「ボタンが赤く点灯していたらエラー」といった判断基準がわかれば、新人が自分の作業が適切かどうかを迷ったり、自己判断で誤った作業を進めてしまうことを防ぐことができます。
問い合わせ先を明記する
トラブル発生時の連絡先や、マニュアルに関する質問の問い合わせ先など、担当者や担当部署の連絡先を明記しておきましょう。
誰に聞けばよいのかがわかると、新人の安心材料にもなり、スムーズに業務を進めることができます。
4.フィードバックを受ける
完成したマニュアルは、配布する前に第三者からのフィードバックを受けましょう。
その際、上司や先輩社員のほか、経験の浅いスタッフにもチェックしてもらうことをおすすめします。新人に近い立場の人にチェックしてもらうことで、わかりづらい箇所や不足している情報がないかなど、実際の読者視点からの改善点を発見しやすくなります。
また、マニュアルは作成して終わりではなく、定期的な見直しが必要です。常に最新の情報が反映できるよう、あらかじめ改訂の時期や担当者などを決めておきましょう。
▼改訂のタイミングや改訂手順については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
まとめ
今回は、新人教育マニュアルの作成方法についてご紹介しました。新人教育マニュアルは、新人が業務をスムーズに習得するためのサポートツールとして役立つだけでなく、教育担当者側の負担軽減にもつながります。
さらに、業務品質の向上や即戦力化も期待できるため、新人だけでなく会社全体にとってもメリットのあるツールです。ぜひ本記事を参考にして、マニュアルを作成してみてください。