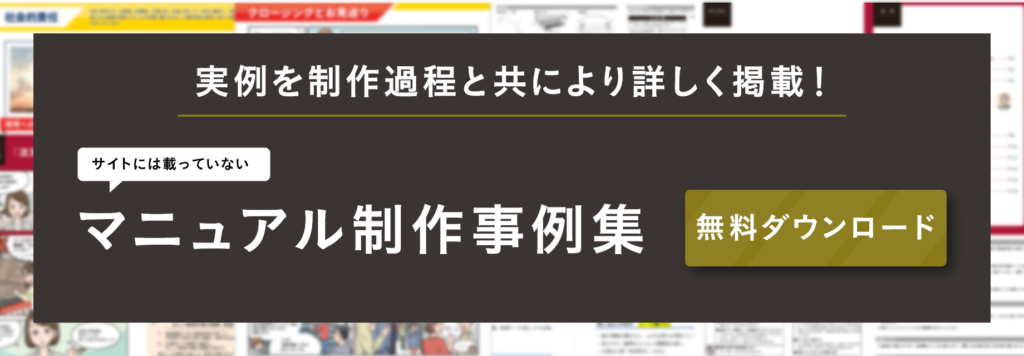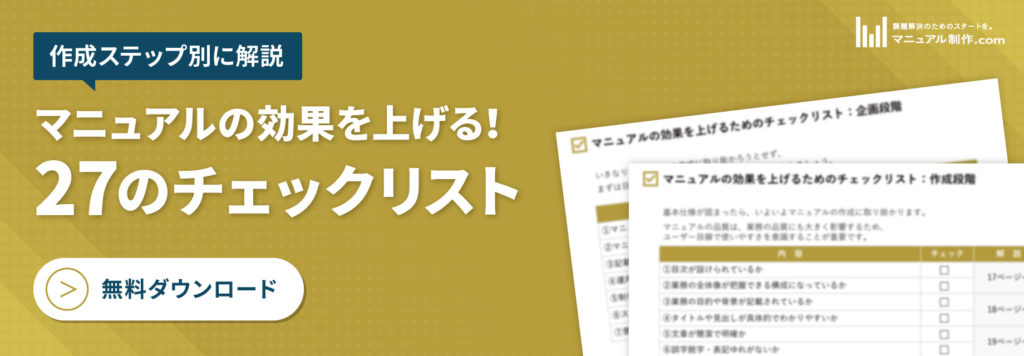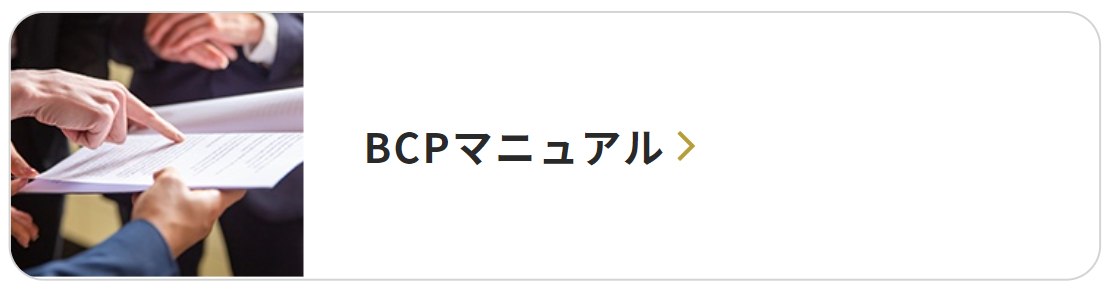目次
BCPとは
BCPとは、Business Continuity Planの略で、事業継続計画のことを指します。
企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。(引用:中小企業庁ホームページ)
なぜBCPが必要なのか
自然災害などの緊急事態は、予期せず突然起こります。そのとき、事態への備えをしていたかどうかによって、復旧にかかる時間・コストに大きな差が生まれます。
BCPは、災害によるダメージを最小限に食い留めるとともに早期に事業を復旧し、継続させるために不可欠な計画なのです。また、BCPの策定によって緊急時の被害を抑えられる企業は市場からも信頼され、企業価値の向上にもつながります。
具体的なBCPの考え方
BCPでは、以下のような手順で計画を策定していきます。
- 最優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する
- 当該事業の目標復旧時間を定める
- 緊急時に提供できるサービスの水準について、事前にクライアントと協議する
- 事業拠点や生産設備、仕入先・仕入方法などの代替策を用意しておく
- 従業員と共有する
こうして書くと簡単なようですが、「2.当該事業の目標復旧時間を定める」の項だけでもこれだけの検討事項があります。
・どの水準までサービスが回復すれば復旧したといえるのかを定義する
例)通常の70%、つまり受注金額○○円分まで対応可能になった時点で復旧とする
・従業員の何割が出社できればよいか
例)100人のうち50人が出社できれば、復旧目標を達成できる
・その出社人数を確保するためにはどのような安全対策が必要か
例)遠方の従業員は会社に宿泊できるよう生活用品を揃えておく/緊急連絡網を用意し、交通機関の影響が少ない従業員から出社を促す
・生産設備がどれだけ稼働すればよいか
例)生産機械が通常の70%稼働すれば、復旧目標を達成できる
・緊急事態の環境下でどのようにして稼働率を達成するか
例)緊急用の電源を別途確保しておく/耐震補強を行っておく/緊急時の操作マニュアル、トラブルシューティングを充実させる
・故障している場合にはどうするか
例)メーカーの修理を呼ぶ/メーカーが稼働していない場合は自社従業員が対応する→そのために日ごろからメンテナンス技術を習得する
・復旧目標達成に必要な原材料の仕入はどうするか
例)今のうちから仕入先との間で緊急時の取り決めをつくっておく/在庫をもつ/他の地方にも仕入れルートを用意する
・製品を販売する場合、どうやってクライアントに届けるか
例)宅配便/バイク便/自動車/自転車/公共交通機関/徒歩/それでも無理な場合はどのような案内を出してクライアントの損失を抑えるか
上記はほんの一例です。これらの検討事項について、現状はどこまでできていて、目標を達成するためには何を備えておかなければならないかというところまで落とし込んだ上で実施します。
BCPマニュアルの作り方
一連の手順を踏んでBCP計画が完成したら、マニュアルに落とし込みます。
BCPは経営者やマネージャーだけが理解していればよいものではありません。全従業員で自社のBCPを共有するためマニュアルで文書化する必要があります。
マニュアルは、どの従業員が読んでも分かりやすいようにつくっておく必要があります。特に以下の点に注意しながら作成します。
言葉の言い回しや文章表現・表記
例えば、自部署ではよく使っている言葉が他部署では耳慣れないということも往々にしてあります。社内の立場の違いで使っている言葉の捉え方が変わることもありますので、できるだけ全社共通の言葉で書くようにします。方法の一つとして、社外の第三者にインタビューと執筆を依頼することで客観性の高い文章になりやすくなります。
写真や図、イラストでの補足
例えば、避難経路や防災グッズの保管場所などは文章だけではなく、写真で説明したほうが分かりやすいことが多いです。避難場所の地図や周辺の写真などを付けておくことで実用性の高いマニュアルになります。
写真・イラストなどのビジュアル面の特性を踏まえたマニュアル作りをしましょう。
見出しの整理
マニュアルの内容に応じて見出しのランクを何個か用意し、全マニュアルで統一して使用するようにしましょう。文字の大きさや飾りなどでメリハリをつけ、ページを開いた瞬間に読み手が内容をパッと理解できるのが理想です。
書類としての使いやすさ・保管のしやすさ
せっかく作り込んだマニュアルでも、使いにくければ書類ボックスの奥底に封印されてしまい日の目を見ることがなくなります。それでは意味がありません。
まず、書類のサイズはA4サイズがオススメです。これは書類のサイズとして最も一般的であるという理由からです。
また、マニュアルによってはページ数が増え、分厚くなってしまうことも間々あります。読み手が必要な情報にすぐにたどり着けるように、目次づくりやインデックスタブを付けるようにしましょう。
BCPマニュアルの運用方法
BCPは、一度に全てを完成させられるものではありません。策定中に、すぐに決定できないことも多く挙がってくるはずです。こうした検討事項は一旦保留として、まずは出来るところから策定を進め、マニュアル化していきます。
マニュアル配布後は、関係者を集めて定期的なミーティングを行い、保留にしていた検討事項を決めていきます。計画が確定したら、マニュアルも併せて更新します。従業員各々が自分で最新版に差し替えられるような社内の仕組み・体制…例えば、最新版のマニュアルを社内でダウンロードできるようにしておくなど…をつくっておくと、効率的な更新ができます。
なお、マニュアル制作.comを運営している第一資料印刷株式会社は、東京都のBCP推進事業「東京都発 チーム事業継続」に参画しております。BCP策定およびマニュアル制作に関わるご相談をお受けしていますので、BCPに関してお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。